|
さあ殺そう、どんどん殺そう、右手平の皮がすりむけるくらい、返り血の重さで倒れるくらい、残響だけ残して、絶叫を踏みつけ、嘲弄さえ浮かべずに、実に真剣に、 私は涙とか鼻水とかその手のもので顔中を汚した男の恐怖する呻き声に鈍色にひかる刀身を振り下ろした。 造作なくふたつになった顔を造作なく革靴の爪先で転がして、私は前方へとただひたすら歩を進め、血脂をしたたらせる鋼色を振り下ろし、振り上げ、また振り下ろす。 しかし私の眼球の裏側にはその、或いはその前の、或いはその先の、男のどろどろに歪んだ泣き顔がひどくくっきりと焼き付いていて、 今になっても僅かばかりも褪せることはないのであった。 それらの顔はときどき夢枕に立って、ただひたすらに私をじいっと眺めて、何をするでもなくじいっと。 そうして私の浅い浅い眠りをさらに浅く浅くして、それが目的だったと言わんばかりにふっと薄らいで唐突に消えてしまうので、私はやり場のないひどい虚脱感をそのままに醒めた目で暗い天井を眺めることしかできない。 そのままじっとりと、窓の外が白んでくるまで私は一睡もすることができない。 「それは病気だよ、」 ニューローシスというやつさ、と父親の方のスミルノフは藪医者然としてどこかたのしそうにのたまった。 そのセルロイドの縁が支える分厚いガラスの奥の目玉にはいつもの胡乱なひかりがけぶっているだけで、ああこいつは藪でも医者なのであると私は妙に得心のいった心持ちで少しだけ目を細めた。 「ばけものばけものとおもっていたけれど、君も一丁前ににんげんさまなんだねえ。やだな、そんな怖い顔しないでおくれよ、剣呑だなあ」 僕は生身のお医者様なのさ君と違ってね。スミルノフ医師はカルテとおぼしき紙に安ボールペンを走らせた、カリカリカリカリ、と私は何か頭蓋を削られるような心地がした。 書きながら医師はすんすんと場違いに陽気な鼻歌を歌った。 「いつ頃から眠れなかったのかな、たしか君は眠りが浅いほうだったよね」 「不眠気味なのは持病ですよ、ずうっと。ただ、ここひとつきは特に酷くて、」 「玄人に看てもらおうと考えたと、たしかに君って薬効きにくい体質だしね、ふうん、なるほど」 カリカリカリカリ。 「しかしながら」医師は伏し目のままでつぶやいた「君みたいな奴が僕みたいなのに泣きつくなんて、よっぽど参っていたんだねえ」 眠れぬ夜はつらかったかい、と愉快そうに私の目の下にできた隈を無遠慮になぞる医師に私はとうとう堪忍袋の緒という奴が切れる音をたしかにかんじた。 私はペン差しに立てられているピンセットを抜き取り手の中で一回転、医師がその間抜け声にて、あ、と言う間もなく彼ののど元にその尖ったステンレスを突き立、 「医者は患者をころしちゃだめだと思います、一般的に」 「黙りなさい。さっさとその危険物を父さんから離しなさい」 、てようとして、首筋のきっちり頸動脈横にあたるひやりとした金属に断念をした。 目線で振り返ると、銀色のメスがぴったりと私の首筋に寄り添っているのが見えた。その凶器に絡まる血色の悪い指先をたどるとスミルノフの息子と目が合った。相変わらず、目つきが悪い。こちらのほうがよっぽど剣呑である。 私は左手のピンセットをゆっくりとおろした。スミルノフ息子もメスをゆっくりとおろした。 「だから言ってるじゃあないですか、父さん、こんな物騒な奴のこと看てやることなんてないって。ほうっておきましょうよ、神経病ごときじゃあ死にやしませんよこのばけものは」 「だっておもしろいじゃあない、気をちがえたばけものなんて」 「ばけものばけもの、でかい口叩いてるんじゃないですよきちがい無免許医親子が。私が善意の通報ひとつすればあなたたちは光の速さで塀の中です」 「だから、黙りなさいと言ってるでしょう、僕たちがいなければ不眠のひとつも治せないくせに。動脈切開して末永く快眠させてあげようか、今すぐに」 親が親なら息子も息子、蛙の子はやはり蛙である。私はひどい倦怠感に重々しい溜息をついた。 「もうあなた方の数々の暴言の類にはこの際目をつぶりますけれど、」我ながら寛容の域を超えている「とりあえずなんでもいいので薬だけください、薬さえいただければ何も言わずに帰りますので」 息子のほうはさっさと帰れという顔つきを隠しもせず頷き、父親のほうはものすごく残念そうにえぇ、とごねた。 「もっとこうカウンセリングとか臨床心理テストとかしたかったのになあ。あと催眠療法とか薬物投与とか。ねえ僕、君の体は勿論だけれど頭の中にもすごく興味があるんだよ」 「やめてくださいよそういういかがわしい言い回し、気持ち悪い」 「父さんを悪く言うんじゃありません干物野郎」 「あなたこそそろそろ黙らないとうっかり手が滑って顔が真っ二つになってしまうやも」 真っ二つ。この男はおそらく真っ二つになる直前でも涙どころか汗の一滴も流しはしないのであろう。そして夢枕では積極的に私の首筋の血管の束を断ち切ろうと立ち回るに違いない。 「気色悪い、」 読心したかのように息子は眉間に縦皺を寄せて、吐き捨てた。たしかにたいがい気色悪い。 「じゃあちょっと待ってなさいな、薬出してあげる。友人特別価格で三割増し増しで売りつけちゃうからね」 スリッパをぱたつかせながら乳白色のリノリウムの床をかけてゆく背中を私はぼんやりと見送った。 「罪には罰を」 視線をよこすと、例の冷え切った貴金属みたいな色をした目をして息子は蔑むように嗤った。 「せいぜい苦しみなさい」 まるで神父みたいなことをいうのだな、と私は、ああそれもそうですねと作り笑いを浮かべてみせた。 用法用量を守ってただしく御服用ください。という黒々としたゴチック体を尻目に、私は白色の錠剤をみっつほど一気に飲み下した。のど元を異物が通っていく感覚にああこれが毒だったら、と無駄なことを考えた。 それで? 「立つか、さもなくば死ね」 せいぜい苦しみなさい。それはたしかなことだ、と私は自分の黒色に塗られた十の爪を眺めた。そもそも私に毒なんて効かない、それは終わりのないことのように思われた。 耳の裏側に掠れたような絶叫が聞こえた。ああ。私は緩慢に寝室へと脚を進めた。 (さあ殺そう)(ああ殺して) なんてつまらない、白色の冷え切ったシーツに私の眼球はゆっくりとした痙攣をはじめた。 その男たちは涙と鼻水を垂れ流しながら最後のさいごまで私の顔を見て私の顔を見ながらそのまま縦一直線に、 ああそれもそうだ、と私の意識はそこで途切れた。 |
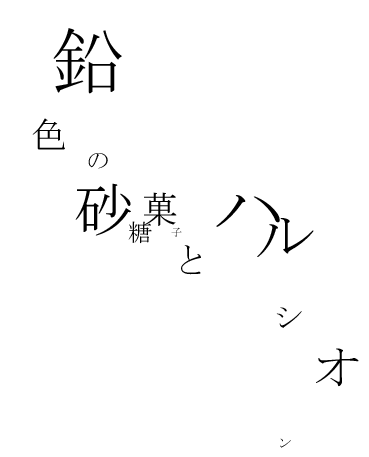
(c)kasako 10.10.18